
モールテックス 主材カラー2N 25kg
¥24,860

サカンアートが編集するコラムや、
お客様よりいただくよくある質問にお答え

モールテックスは、店舗や企業、施設だけでなく、一般住宅に取り入れる動きが活発化しています。施工場所も、キッチンや塗り壁に加え、リビングにも使われるようになっています。こちらでは最初にモールテックスの特性を説明し、モールテックスを施工する際の失敗しないコツをご紹介します!
【今回の記事のポイント】
✔︎ モールテックスについて知れる
✔︎ モールテックスを施工する際に失敗しないコツを知れる
更新日:2023/2/7
初稿:2020/3/1
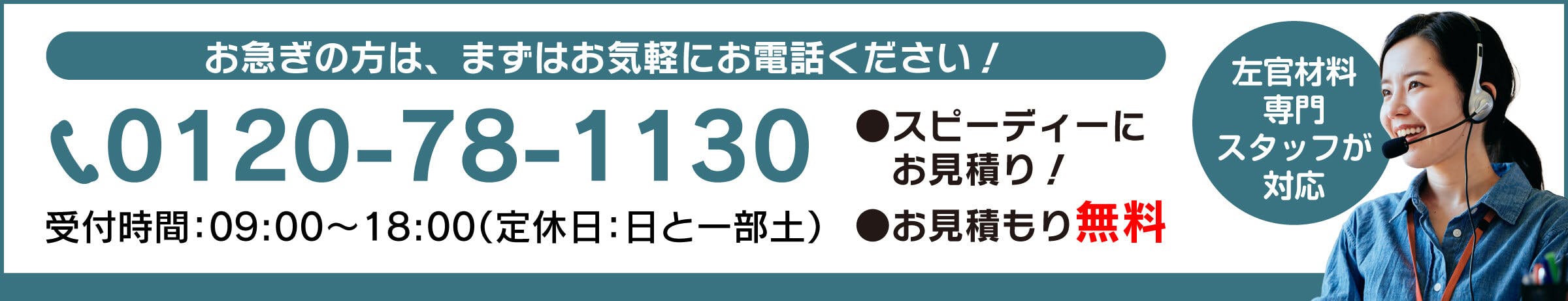
モールテックス(mortex)は、ベルギーのBEAL社が開発した左官仕上げ材です。材料はモルタルとほとんど同じですが、特殊な樹脂が混ぜられています。そのため、モルタルと比べると滑らかさや艶が感じられます。

モールテックスは、カラーバリエーションが豊富です。それぞれのカラーを混ぜて使うこともできるため、オリジナルの色合いにすることも可能です。無限に色を作り出せるのが、モールテックスの特徴といってよいでしょう。要望に合わせて色味を調整できるため、顧客満足度は高くなるに違いありません。
⇩⇩カラーバリエーションはこちら⇩⇩

モールテックスの別の特徴として、防水性が挙げられます。左官材料だけで、浴室など水回りの施工が可能になる点が、モールテックスの良いところです。防水性を生かして、シャワールームや洗面台に加え、キッチンのシンクや塗り壁、カウンターやテーブルなどの施工も増えています。水回りのデザインは、ある程度画一的なものになりがちですが、モールテックスを使うことでカラーバリエーションの幅が広がり、個性を打ち出せます。

モールテックスは高い防水性を維持しながら、薄塗りができます。わずか2ミリから3ミリ程度の施工でよいため、室内の広さや建物の強度に影響を与えることはほとんどありません。モールテックスは、モルタルのような「ヒキ」が見られず、乾燥しても割れにくいのが特徴です。実際、モールテックスの強度は、コンクリートの数倍あるとされます。下地がしっかりしていれば、衝撃にも十分耐えられますし、耐熱性も期待できます。

モールテックスは施工する下地を選びません。鉱物下地に加え、木や金属、タイル、スタイロフォーム、メラミン、ビニールクロスなど、あらゆる場所に施工できます。そのため、床や階段、ガレージなど、さまざまな場所に使えます。扱いに慣れれば有用な素材で、重厚感を感じられる素材の特徴を生かし、建築物だけでなく、テーブルなど備品類にも使われるようになっています。
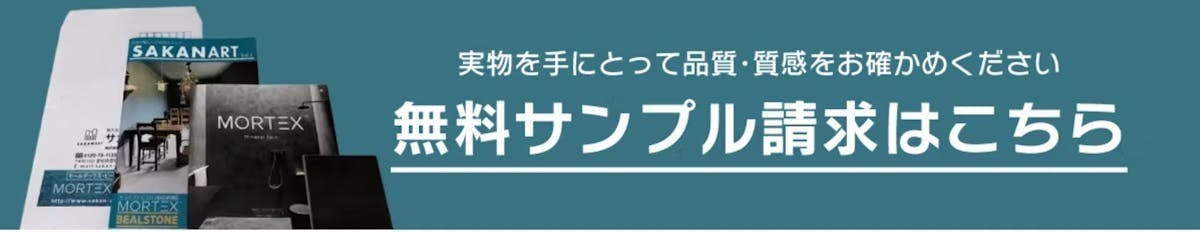
モールテックスは、リノベーションの際の施工材料としても注目が集まっています。通常はタイルなどを除去してから新しい材料での施工が必要ですが、モールテックスを上からかぶせるように施工することで、工事にかかる時間や下地の除去にかかる作業コストも減らせるからです。
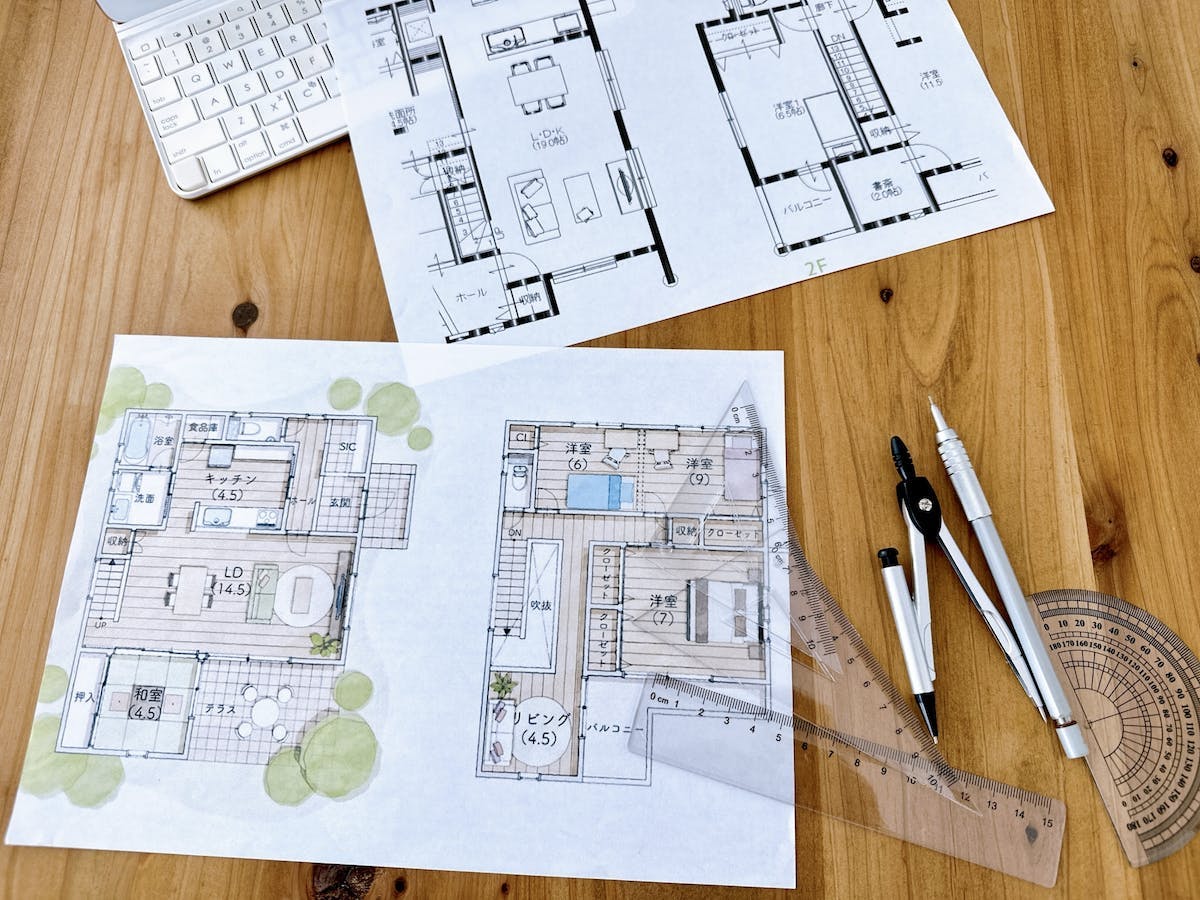
モールテックスは、他の材料の施工に比べて費用が高く感じる傾向にあります。そして、モールテックスは作業工程が複雑と思われがちです。そこでこれからはモールテックスを施工する場合の失敗しないコツをご紹介します!
ここからはモールテックスを施工するにあたり失敗しないコツを3つ紹介していきます。


左官材料モールテックスの主材(粉体)の袋を開けるときは上下があります。袋を縦において袋外に表示してある文字が、正しく見える方を上にして合わさったところを空けると薄い青い紙があります。それを矢印の方向に開けるときれいにはがせますので、もし材料が残った場合でも、そこをきちんと閉めておけるので、持ち運びや管理が容易になります。

左官材料モールテックスの顔料は溶けにくい色があります。それを先に主材に混ぜてしまうと液と合わせた時でも混ざりきらずに塗りつけしたときにダマとして残ってしまうことがあります。それを防ぐ方法が先にビールクリルに溶かしておくことです。顔料が水分を含んで溶けやすくなりますし、主材をすべて一度に入れるのではなく、3分の1ほど入れて一度混ぜ合わせることで、顔料のダマもつぶれやすくなり、混ぜ合わせがとても楽になります。

左官材料モールテックスは、練りダルで練るよりもバケツで練ることが多くなると思います。その時に選ぶバケツは底に段のついたものではなく、できるだけ丸いものを選ぶのがコツです。練り混ぜの残りが出にくくなりますし、材料を全部取りきることが容易になります。さらにモールテックスは、バケツに結構こびりつきますので、100円均一などで、安くいバケツをさがして、使い捨て感覚で使いましょう。
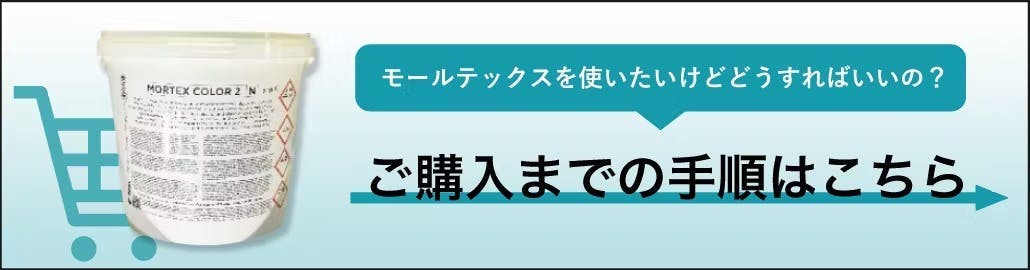

モールテックスを施工する際のコツをご紹介してきました。施工するコツ以外に施工方法をさらに詳しく知りたい方向けに講習会をおすすめしています。
モールテックス基本講習会では、日本で3人しか認められていないモールテックスの講習官が、一日を通してみっちりレクチャーします。
モールテックスの基本情報や特徴、性質などについて学んでいただく座学。実際にモールテックスを施工していただく実技の部とに分かれます。

ここまでモールテックスの失敗しないコツをご紹介してきました。モールテックスは作業工程が複雑と思われがちですが今回ご紹介したコツを意識しながら施工をしてみてください。
また、サカンアートでは初心者向けや初めて扱う業者様向けに講習会や動画での解説を行なっております。こちらを受講することで認定を受けたのと同様に材料を扱うことができるでしょう。
サカンアートでは施工業者の紹介も行なっております。施工業者を紹介して欲しいという方に対してなるべくお近くの施工業者様をご紹介させていただいています!お気軽にお問い合わせください。
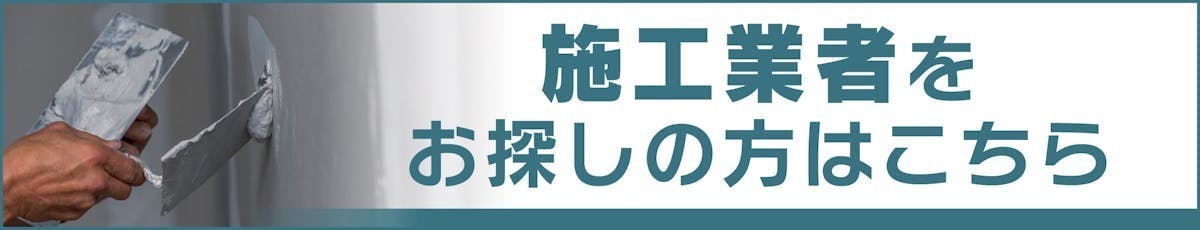
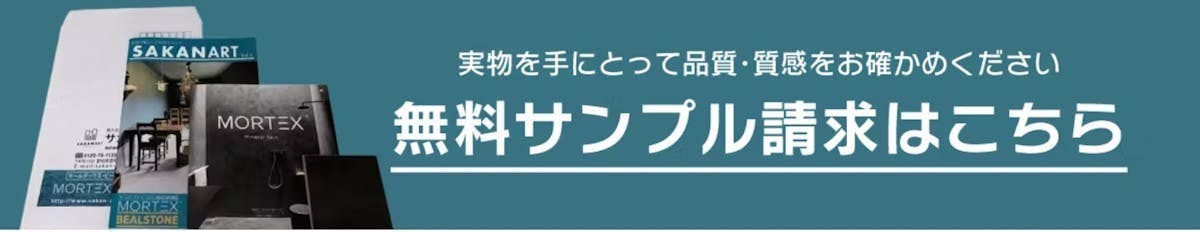

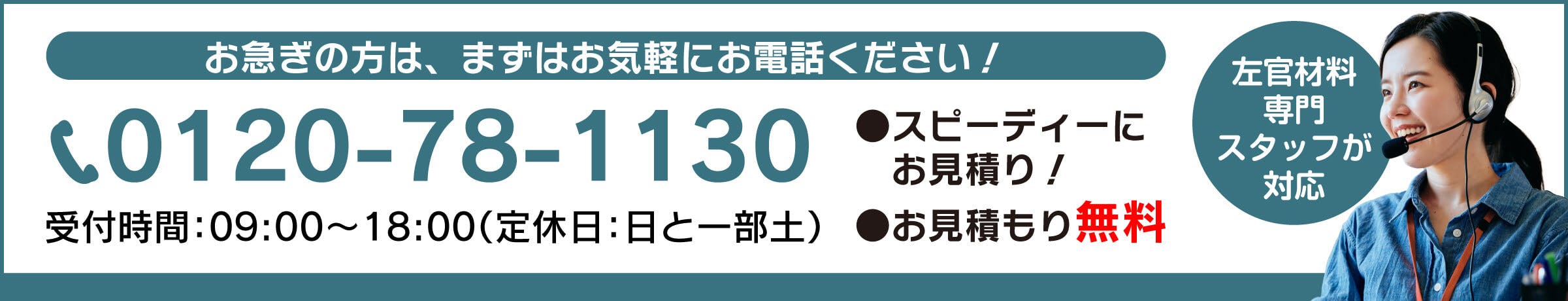

サカンアートが編集するコラムや、
お客様よりいただくよくある質問にお答え
PICK UP

「水回り=機能性重視で見た目は二の次」そんなイメージ、まだ持っていませんか?

「公共施設の床って、なんだか無機質でつまらない」そう感じたことはありませんか?

近年、空間デザインのキーワードとして注目を集めているのが「デザインコンクリート」。

「本物の打ちっ放し感を出したい」「内装に高級感を持たせたい」そんなデザインへのこだわりを持つ方に、